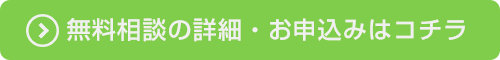���`�O�Ȃ̊J�Ǝ����E���Ȏ����E�N���E���s����
���`�O�ȃN���j�b�N�̊J�Ǝ���
| �y�n�A���� | ��3,000���` |
|---|---|
| ���� | ��5,000���` |
| �ݔ� | ��1,900���`2,500���~ �d�q�J���e�A���W�X�^�[�A�R�s�[�����@�i�ƒ�p�j�A�f�@�p�x�b�h�AX���B�e���u�ADICOM�i�_�C�R���j�摜�������鍂���׃��j�^�[��PACS�A�摜�ǂݎ�葕�u(CR�ADR�V�X�e��)�A�{�p��E���n�r���@�� �Ȃ� |
| �^�]���� | ��2,500���` |
�e�i���g�J�Ƃ�1���`1.5���A�ˌ��ĊJ�Ƃ�2���`2��5,000���~���x���J�Ǝ����̖ڈ��ɂȂ�܂��B
���Ȏ������Ȃ��Ă��J�Ƃ͂ł���H
��L�̊J�Ǝ����́A�搶���S�z���Ȏ����Ƃ��ėp�ӂ�����̂ł͂������܂���B�e�i���g�J�Ƃł���A���Ȏ���0�ł��J�Ƃł��܂��B
�ˌ��ĊJ�Ƃł́A�y�n�����_��i���Ɨp����ؒn���_��j�����сA�����̌��݂�ݔ��̏������s���ꍇ�A���Ȏ����͍Œ�ł�1,000���~���x���K�v�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B �������A�M���ł���ۏؐl������ꍇ��A�e���y�n��p�ӂ��Ă����ꍇ�ɂ́A���Ȏ������Ȃ��Ă��J�Ƃ��\�ɂȂ�P�[�X������܂��B
�ڂ����́A�J�ƂɊւ���悭���鎿��Q��A�u���Ȏ����͂ǂꂮ�炢��������H�v���������������B
���`�O�Ȃ̎��x�i1�J��������j�ƔN��
�l�N���j�b�N�̎��x�i1�J��������j�ƔN��
| ���v | |
|---|---|
| �f��V | ��845���~ |
| �����v | 3���~ |
| �o�� | |
| �l���� ���@���̎����͊܂݂܂��� | ��293���~ |
| ���i�� | ��106���~ |
| ���̑� | ��224���~ |
| ���`�O�Ȃ�1����������̎����i���v - �o��j= ��225���~�i�N���F��2,700���~�j | |
�����J���� �����Љ�ی���Ë��c�� ��24���Ìo�ώ��Ԓ����i��Ë@�֓������j�|�ߘa5�N���{�| p.150 ���Q�l�ɏW�v
��Ö@�l���x�i1�J��������j�ƔN��
| ���v | |
|---|---|
| �f��V | ��1,237���~ |
| �����v | ��52���~ |
| �o�� | |
| �l���� ���@���̎������܂݂܂� | ��717���~ |
| ���i�� | ��146���~ |
| ���̑� | ��362���~ |
| �ň���̐��`�O�Ȃ�1����������̎����i���v - �o��j=
��64���~�i�N���F��768���~�j �������搶�Ɨ����i���l��l�������q�l�j�̕�V���������A�c��̈�Ö@�l�̎����ł��B |
|
�����J���� �����Љ�ی���Ë��c�� ��24���Ìo�ώ��Ԓ����i��Ë@�֓������j�|�ߘa5�N���{�| p.162 ���Q�l�ɏW�v
���`�O�ȃN���j�b�N�J�ƈ�̎���
���`�O�ȊJ�ƈ�̐\�������́A��]�ҋ��^���x��������ł�2,000���~�ȏ�ƂȂ�̂���ʓI�ł��B
����ɁA���ЃN���C�A���g�̎����I�ȕ��ϔN����5,000���~�ȏ�ɒB���Ă��܂��B
�������A�����̏ꍇ�A��Ö@�l�����s�����߁A�\����̔N���͒Ⴍ�v�Z����܂��B
���̎d�g�݂ɂ��ďڂ����m�肽�����́A�u��Ö@�l�v�ɂ��Ẳ�������������������A�������k�������p���������B
���`�O�Ȃ̊J�Ƃ̃|�C���g
���ʂȐݔ������͂��Ȃ�
�K�v�ȏ�̐ݔ�������ƁA�J�Ɣ�p���c��݁A�N���j�b�N�o�c�ɕ��S���������Ă��܂��܂��B
�Ⴆ�A�E�H�[�^�[�x�b�h�^�}�b�T�[�W�@�́A�����R�X�g�ɑ��āA�\���Ȏ��v���m�ۂ���̂�����ݔ��̈��ł��B
�w������ݒu�X�y�[�X�𑽂��K�v�Ƃ��A����ɔ����^�c�R�X�g���������Ă��܂��܂��B �܂��́A���������ݔ���i�߂�Ǝ҂̒�Ă����̂܂����O�ɁA�f�Õ��j��̎Z���A�n�搫��T�d�Ɍ������邱�Ƃ��d�v�ł��B ���ʂȎx�o��}���邱�ƂŁA�������I�Ȍo�c���\�ɂȂ�܂��B
�u���m�v�ł͂Ȃ��u�q�g�v�ɓ�������
���`�O�Ȃ̊J�Ƃł́A�f�Õ�V�̌n�𗝉������J�Ɛ헪���d�v�ł��B ���ɁA�^���탊�n�r���e�[�V�������̎d�g�݂�c�����A�l�ނ��ő�����p���邱�Ƃ��o�c�̃J�M�ƂȂ�܂��B
�^���탊�n�r���e�[�V������
1�P�ʁi20���j���ƂɈȉ��̓_�����Z�肳��܂��B
- �^���탊�n�r���e�[�V�������i�T�j�F185�_
- �^���탊�n�r���e�[�V�������i�U�j�F170�_
- �^���탊�n�r�e�[�V�������i�V�j�F85�_
- �Z����ԁF���̏ꍇ�A150�������x�Ƃ��ĎZ��ł��܂��i��t���̌����݂�F�߂�Ή������ł��܂��j
- ���{�P�ʐ��F1��������]����1�l�ɂ�18�P�ʁi���24�P�ʁj�A�T�ő�108�P��
���w�Ö@�m�ւ̓���
���w�Ö@�m���ق����ƂŁA���n�r���������悭�Ȃ���A���҂̖����x�����コ����ƂƂ��ɁA�o�c�̈��艻�ɂ��Ȃ��邱�Ƃ��ł��܂��B �n��ɂ���ċ��^�����͈قȂ�܂����A1�ԍ��������ł��\���ɍ̎Z�������悤�ɐݒ肳��Ă��܂��B
���ː��Z�t�̗̍p�ɂ���
�J�Ǝ��_������ː��Z�t�̗̍p�����������t����������Ⴂ�܂����A������x���҂�����I�ɗ��@����܂ł͕K�v����܂���B���ː��Z�t�̋��^�͍��߂ŊJ�Ǝ��͋Ɩ��ʂ����Ȃ��ɂ����ė]���܂��B
�J�Ǝ��͈�t���S�ŎB�e���s���A�J�ƑO�̌��C�ŊŌ�t�Ƀ|�W�V���j���O�������Ă������Ƃ⊳�҂̒��ւ��ȂǑz�肵�����������O�ɍs���Ă������ƂŌ����I�ɑΉ��ł���悤�ɂȂ�܂��B
�K�v�Œ���̐ݔ���
�����g�Q���A�摜�ǂݎ�葕�u(CR�ADR�V�X�e��)�ADICOM�i�_�C�R���j�摜�������鍂���׃��j�^�[��PACS�A�����x�v�A�d�q�J���e������A���Ƃ͎{�p����w�����邮�炢�ł��傤�B
�܂��A�L�����n�r���X�y�[�X���m�ۂ��邱�ƂŁA��قǐ�������݂Ȃ��ʏ����n�̓���������ɓ��ꂽ�o�c���\�ɂȂ�܂��B ���n�r���@��ŃX�y�[�X�߂�̂ł͂Ȃ��A�l�ނ̊��p�𒆐S�Ƃ����^�c��ڎw���܂��傤�B
�����g�Q���@��̓V�䑖�s���ɂ���
�����g�Q���@���V�䑖�s���ɂ��邱�Ƃŏ㉺���E�̃X�g���[�N���傫���Ȃ�̂ŗl�X�ȎB�e�p���ɑΉ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�܂��C�ӂ̊p�x�ŌŒ�ł��A���G�Ȋp�x�̎B�e���\�ƂȂ邽�߈�ÃX�^�b�t�⊳�҂̕��S�y���Ɍq���邽�ߌ����������オ��܂��B
��ʓI�ȕǑ��s���Ɣ�r����Ƌ@���H����p�̕��S�͑����A�����̏ɂ���Đݒu�ł��邩�ǂ����Ƃ����m�F����������܂����A��x��������Ɠ���ւ�������@��̂��ߐ�����z���Č�������悤�ɂ��܂��傤�B
�R���Z�v�g�ɍ��킹�������x�����@�퓱��
�N���j�b�N�̃R���Z�v�g�ɍ��킹�A�����x�����@��̓������������܂��傤�B �����x�����͍̎Z�����₷���������ڂ̈�ł��B
�Ⴆ�ADEXA�@�ɂ�鍘�ŎB�e�ł�360�_�A�����ɑ�ڍ��̎B�e���s���ꍇ�́A�����90�_�i��ڍ������B�e���Z�j���Z����܂��B
���̂悤�Ȑf�Õ�V�̎d�g�݂́A���e���傤�Ǘ\�h�����̈�Ô�팸�ɂ��Ȃ����Ă��邽�߁A�傫���ύX�����\���͒Ⴂ�ƍl�����܂��B �������A��T�ɓ������ׂ��Ƃ����킯�ł͂���܂���B
����҂��^�[�Q�b�g�Ƃ����J�ƃR���Z�v�g�ŁA���e���傤�Ǘ\�h�̎��v�������߂�n��ł���A�����̉��l�͏\���ɂ���܂����A��N�w��Ώۂɂ����R���Z�v�g�̏ꍇ�A�����x�����̎��v�͏��Ȃ����Ƃ��������߁A�X�|�[�c���`�O�ȂȂǑ��̐f�Õ���ɏd�_��u���I����������܂��B
��������������ۂɂ́A�N���j�b�N�̃R���Z�v�g��n��̃j�[�Y�Ƃ̐���������������ƌ��ɂ߂邱�Ƃ��d�v�ł��B
�݂Ȃ��ʏ����n�Ƃ�
���N�ی��@�̕ی���Ë@�ւɎw�肳�ꂽ�f�Ï��́A���ی��@�ɂ���Ìn�T�[�r�X�̎��Ǝ҂Ƃ��Ď����I�Ɏw�肳��܂��B���̎d�g�݂��u�݂Ȃ��w��v�ƌĂт܂��B �݂Ȃ��w������p���邱�ƂŁA�������n�r���X�y�[�X���g�p���A�������w�Ö@�m���^����̒ʏ����n�r���e�[�V�������s�����Ƃ��\�ɂȂ�܂��B���ꂪ�u�݂Ȃ��ʏ����n�v�ƌĂ�鐧�x�ł��B
�݂Ȃ��ʏ����n��������邩�ǂ����́A���`�O�ȃN���j�b�N�̌o�c�헪�ɂ�����d�v�ȑI�����ƂȂ�܂��B
�݂Ȃ��ʏ����n�̓���
���n�r���e�[�V������������Ԃɐ������Ȃ�
��Õی��̏ꍇ�A�K�v�ɉ�����150�����ĉ^���탊�n�r���e�[�V�������p�����邱�Ƃ��ł��܂����A���̍ہA���җl1�l������ɎZ��ł���P�ʐ��͌�13�P�ʂ܂łƐ�������Ă��܂��B
����A���ی��ɂ��݂Ȃ��ʏ����n�r���e�[�V�����ł́A���p�҂����n�r���e�[�V������������Ԃɐ���������܂���B
���w�Ö@�m1�l�ɂ��A10�l�̃��n�r�����ɍs�����Ƃ��ł���
��Õی��ɂ��^���탊�n�r���e�[�V�����ł́A���w�Ö@�m1�l�������ɕ����̗��p�҂Ƀ��n�r������邱�Ƃ͂ł��܂���B
���ꂪ���ی��ɂ��݂Ȃ��ʏ����n�r���e�[�V�����ɂȂ�ƁA���w�Ö@�m1�l�ɂ��ő�10�l�̗��p�҂̃��n�r���e�[�V�������ɍs�����Ƃ��ł��܂��B
���̏ꍇ�A���p��1�l�ɂ�3�u�̃��n�r���e�[�V�����X�y�[�X���K�v�Ƃ���܂��B �Ⴆ�A�^���탊�n�r���e�[�V�����U���擾���Ă���A���w�Ö@�m2�l���ݐЂ��Ă���ꍇ�́A60�u�̃X�y�[�X���K�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�Ȃ��A��Õی��̃��n�r���e�[�V�����Ɖ��ی��̃��n�r���e�[�V������X�y�[�X�Ŏ��{���Ă���ꍇ�A�݂Ȃ��ʏ����n�r���e�[�V������1����̗��p���Ԃ�2���Ԗ����ɐ�������邽�߁A���ӂ��K�v�ł��B
��Õی�������ی��ւ̈ڍs�𐄐i
����A�ێ������n�r���e�[�V�����ɂ��Ă͈�Õی�������ی��ֈڍs����������������J���Ȃ����������Ă��܂��B
���������āA�݂Ȃ��ʏ����n�r���e�[�V������S�����������ɁA�����Ö@�̈�Ë@������߂��邪�܂܍w������ƁA�ߑ哊���ƂȂ莸�s�������\��������܂��B
���`�O�Ȃ̎��s����
���Ђ����ɂ������`�O�Ȃ̎��s��������Љ�܂��B ����搶���w�O�ł̊J�Ƃɂ������A���ԏ�̑䐔�m�ۂ⒓�ԏꂩ��̋������\���ɍl�������A�Ǝ҂̊��߂�܂܈�Ã��[���ŊJ�Ƃ����P�[�X�ł��B
���̌�A�w���痣�ꂽ�ꏊ��30�䕪�̒��ԏ����������`�O�Ȃ��V���ɊJ�Ƃ��܂����B ���̐��`�O�Ȃł́A�����Ö@�̈�Ë@��͂قƂ�ǒu�����A�J�Ǝ����痝�w�Ö@�m��2���̗p���A���җl�ɂƂ��Ēʉ@�֗̕����Ǝ��Ì��ʂ̍������]���ƂȂ�A����ɐl�C���W�߂܂����B
����A�w�O�̈�Ã��[���͒��ԏ�̑䐔�����Ȃ��A����Ɏ��ԑтɂ���Ă͉w�O���ӂŏa���������邱�Ƃ�����܂����B
�����ɕs��������鍂��̊��җl�ɂƂ��ẮA�ʉ@���₷���A���җl���Ƃɗ��w�Ö@�m���S�����郊�n�r���e�[�V���������N���j�b�N�̕������͓I�ł���A�����̊��җl���ڂ��Ă��܂����̂ł��B ���̌��ʁA�w�O�̐��`�O�ȃN���j�b�N�ł͊��Ґ���30���ȏ㌃�����Ă��܂��������ł��B
���`�O�ȂŎ擾����{�݊
�J�Ƃ̃R���Z�v�g�ɂ���ĕK�v�A�s�v�Ȃ��̂��������܂��B
�܂��͕��Ђ̖������k�ւ��z����������
���`�O�ȃN���j�b�N�̊J�Ƃ����l���̐搶�ŁA���Ȏ�����f�ÃR���Z�v�g�̌���A�����̑I��⎖�ƌv�揑�̍쐬�ȂǁA���Y�݂�^�₪�������܂�����A�܂��͕��Ђ̖������k�ɂ��\�����݂��������B
���ЃR���T���^���g���搶�̂��Y�݂����������A�K�ȃA�h�o�C�X�������Ă��������܂��B
FP�T�[�r�X�Ő��`�O�ȃN���j�b�N���J�Ƃ��ꂽ�搶�̐�

�܂��͂琮�`�O�ȃN���j�b�N
�@�� �O�� �G�� �搶
�i2020�N�����s���n��ɂĈ�@�J�Ɓj
���͋Ζ���E���ɐҒŊO�Ȉ�Ƃ��āA��p�O��̊��җl�̐f�ÂɊւ���ĎQ��܂����B
��p�ɂ���āA���҂���̏Ǐ�͊y�ɂȂ�A�������Ē������Ƃ��ł��܂������A��p�K���܂łɂ͎���Ȃ������p���S�O����������������܂����B...������ǂ�

�k�˓c�i�m���`�O�ȃN���j�b�N
�@�� ���� ���K �搶
�i2019�N��ʌ��˓c�s�ɂĈ�@�J�Ɓj
���́A���`�O�Ȃ̒��ł��ҒŊO�Ȉ�Ƃ��āA�ҒŎ�p���肵�Ă������Ƃ�����A�����A�J�Ƃ��邱�Ƃ́A���܂�l���Ă��܂���ł����B...������ǂ�